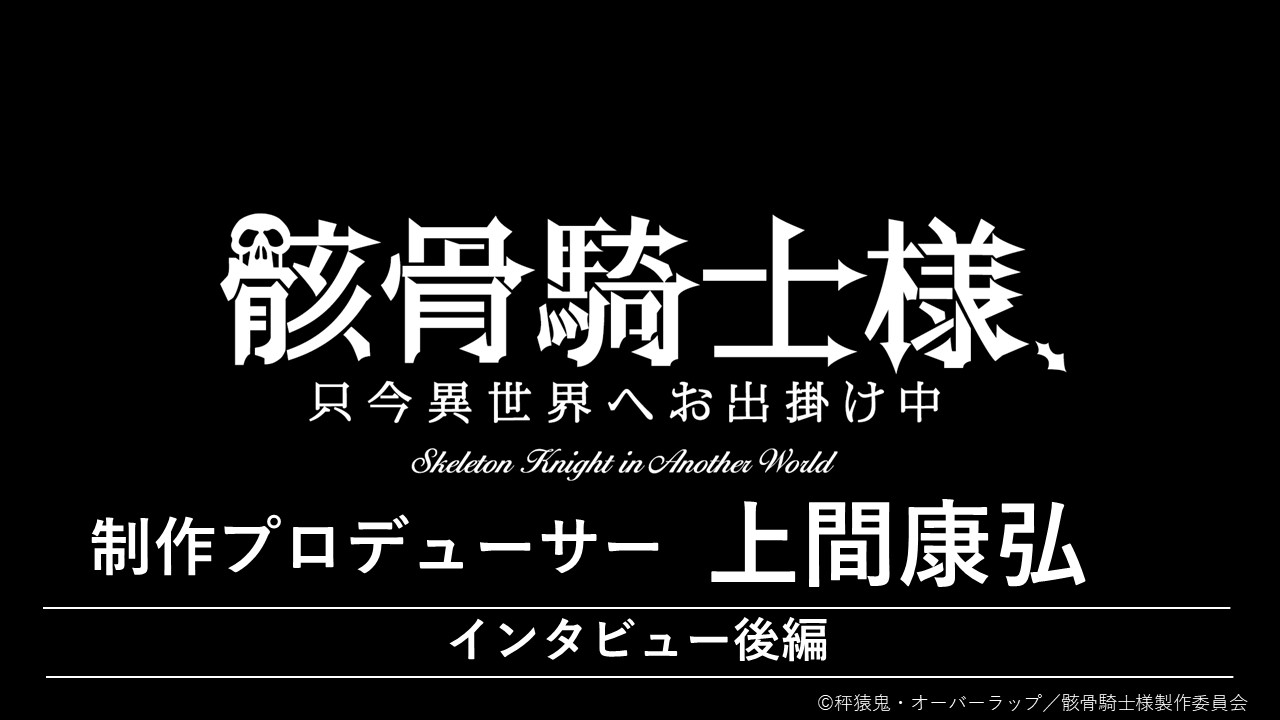『スーパーカブ』 藤井俊郎(監督)インタビュー【前編】

『スーパーカブ』 藤井俊郎(監督)インタビュー【前編】
両親も友達も趣味もない、「ないないの女の子」小熊。
そんな彼女の単調な生活は、ふと見かけた中古のカブを買ったことで、少しずつ変わり始める――。
4月7日より放送が開始される、角川スニーカー文庫にて刊行中のライトノベル作品『スーパーカブ』。
本作のTVアニメ化の監督を務める藤井俊郎に、作品の魅力や特徴について聞いた。前後編でお届けする。
2021年4月2日(金)
■距離感のある作品性
――原作小説を読まれた印象からおうかがいできますか。
藤井 作家の熱意や意図を読者に押しつけ過ぎない、そんな空気感に惹かれました。職業柄、さまざまなライトノベルや漫画原作を読ませていただくのですが、異彩を放っていた印象です。
――小説は第三者視点で描かれていますよね。一歩引いた距離感がお好きだったと。
藤井 ええ。ライトノベルというより、純文学のような作品だなと思いました。ライトノベルや漫画は基本的にキャラクターの感情を押し出しながら物語が進む作品が多いと感じるのですが、『スーパーカブ』は、もっと慎ましいというか。登場するカブも町並みの描写も、小道具ひとつとっても、想像させられるのではなく、自然と想像できるんですよね。これはおもしろい……いや、正確には”好き”になれる作品だなと。すごく自分に刺さったんです。
――それで監督を引き受けられたのですね。
藤井 実は当時、別作品も動いていたので2本同時に監督するのは無理だなと一度お断りしたんです。作品を読むこともせずに。でも『スーパーカブ』というタイトルが妙に気になって。カクヨムで連載をしていたので、そのあと読んでみたんですよ。そこで「これはやってみたい。自分で映像化したい」と純粋に思って。あらためて連絡を入れて、「いまのスケジュールでは無理だけど、半年ずらせないか」と相談を持ちかけたんです。そこでスタジオの担当者の方がKADOKAWAさんと掛け合ってくださって。本当にありがたかったですね。
■隙間や行間にあるものを
――監督としては、本作をどのようなイメージで制作していこうとされたのですか。
藤井 ふたつの作品を指針として挙げていたんです。脚本開発に入るときにシリーズ構成の根元(歳三)さんと共有したのですが、ひとつは、当時放送していた朝ドラの「ひよっこ」です。
――ゆったりした感じでしょうか。
藤井 そうですね。時間の流れや優しい世界感、それとモノローグの使い方です。本編中にキャラの独り言で感情を説明するような演出は避けたかったので、物語冒頭とラストをモノローグで挟んで所感を語る構成にしたいなと。
――確かに、朝ドラではよく見る構成ですね。
藤井 もうひとつは、ジム・ジャームッシュ監督の「パターソン」です。明確なストーリーはなく、詩を読みながらバスの運転手をしている男性の毎日をひたすら丁寧に、淡々と描いている映画なのですが、その眼差しというか、世界の切り取り方がすごく心地良かったんです。この雰囲気でやれると原作の持っている空気感が活かせるんじゃないかなと。
――ゆったりめな間(ま)の取り方も、「パターソン」の影響なのですか。
藤井 それもありますが、大本は『18if』の監督をやったときの演出を踏襲した感じです。
――各話監督制で、藤井さんは第3話を担当されていましたよね。
藤井 はい。あれは、自分が惹かれていた”少し距離感のある演出”というものを、一度アニメのフィールドで試したいと思って制作した作品でした。
――担当された第3話はかなり特殊な演出手法で、非常に印象的でした。
藤井 「好きにやっていいよ」と言われたので(笑)。昔は分かりやすい大作アクションみたいな作品をいっぱい見ていたのですが、歳をとるにつれてこういう演出の作品も好きになっていったんですよね。
そのうえで、『スーパーカブ』の話をもらって原作小説を読んだときに、この方向で作品を組み立てられそうだと思えて。それもあって、お引き受けした面もありました。ですから、『18if』のエッセンスは随所にあります。
――しかし、時間の感覚だけでいえば、『カブ』のほうがゆったり流れている気がします。
藤井 そうですね。『18if』は1話完結の作品だったので、単純にエピソード内の情報量が多いんです。いっぽうで、今回は脚本の段階で意図的にページ数を削りましたしね。
――脚本のページ数が多すぎると、ゆったりした感じが表現できなくなってしまうと。
藤井 (間が)詰まるんですよね。ひと話数のなかで展開するストーリーやサブプロットの物量が多いと、それを尺内に落とし込むので手一杯になるというか。本当は実景を挟んでワンクッション置きたいのに、その尺が取れないから編集でバッサリ切らざるを得ない、なんてことはいろんな現場でザラにあるはず……。
――なるほど。
藤井 役者さんのお芝居が乗って空気が変わることもありますね。これまでも間尺感や空気感、余韻についてはずっと苦労していたんです。ただ、今回は脚本から組み上げられたので、そこはちゃんとしたいし、できるはずと思っていました。でも……やっぱり足りなかったです。
――今回でも足りなかったと(笑)。
藤井 脚本に書かれていないことが絵になるんですよ。いや、書かれていることだけを積み上げても作品として成立するのですが、その隙間や行間にあるものを想像して膨らませたくなるんです。とくに今回は実景ひとつとっても季節感や現地の空気をしっかり落とし込みたくなる。となると、必然的に「ああ、尺が欲しい、尺が欲しい」と(笑)。
■向き合うべき芝居を表現する
――脚本を拝見させていただきましたが、原作小説と比べて、セリフの数をだいぶ調整していますよね。
藤井 見たあとの余韻や映像で描かれなかったものを想像するための余白が欲しかったので、セリフも含めてひと話数の中で展開するプロットの量を、一般的なアニメ作品よりも間引いてほしいとお願いしたんです。けっこう面倒なお願いだったはずですが、さすがは根元さん。原作にある細かなエピソードの取捨選択が本当に的確で、初稿の時点でほぼ決定稿の姿が見えるというか、大きな手直しをする必要がなく、脚本を作るのにほとんど苦労をした記憶がありません。
――その間を保たせるための芝居面ですが、地味ながら難度の高いアニメーションも見られますね。
藤井 (少し考えて)たしかに、こだわってはいます。日常芝居を丁寧に描くのはとても難しいので、TVシリーズではコンテの段階で避ける傾向にありますが、「これは絶対に必要だ」という演出上の信念があるなら、どんなに難しい表現でもやるべきだと思っています。「描くのが大変だから」「失敗しそうだから」と避けていくと表現がテンプレ化してしまいますし。これは「アニメを作りたいなら、アニメばかり見ていてはダメだ」という話にも通じると思います。
――巨匠監督の発言に、時折見られますね。
藤井 リアルな世界では当たり前の動きや描写を、整理しつつデフォルメして表現するのがアニメーションの本質じゃないですか。それなのに、すでにテンプレ化されてしまった表現ばかりを参考にすると、縮小再生産にしかならないと思うんです。個人的にはドラマも映画も大好きなので「実写であればできるけど、アニメでは避ける」という線引きは嫌だった。だから、この作品の世界観を示すために必要なカットや芝居は、大変ですが逃げないようにしたかったんです。
――印象だけでいえば、かなり動き続けている感じがあるのですが……。
藤井 スタッフみんな、本当に頑張ってやってくださいました。ただ、いっぽうで動くところは動くけど、動かないところは一切動かないように設計しているんです。美術単体で見せるカットも多いし、今回は3Dが使えるので作画は一切なしで完結するカットも作っています。そうやって全体のバランスを取りながら進めていきました。
――カブは3Dで制作されていますよね。
藤井 この作品においてカブの描写は本当に大切なものだし、全編通して作画でやるのは現実的ではなかったので、カブに関してはしっかり3Dモデルを起こして欲しいと相談しました。
――3Dモデルであれば、崩れることはないですからね。
藤井 ええ。とはいえ、カブが3Dでキャラが作画というハイブリッドな環境になると、それはそれで難度が高くなってしまいます。そこでキャラの描写は、寄りは作画、ロングは3Dと使い分けをしています。3Dのキャラはロングショットでの使用を前提にして、細かなリギング(動かすための仕組み)やモデリングの必要のない簡易モデルを作成してもらいました。
――それぞれの素材の質感にもこだわりがあるように見えたのですが、3D、美術、セルをどのように融合していったのでしょうか。
藤井 2Dと3Dのハイブリッド作品では、作画と3Dの質感が合わなかったり、今回のような写実的な背景と組み合わせたときにキャラが浮いて見えたりすることもままあります。各セクションがそれぞれ独立して作業を進めているので、最終的に素材を組み合わせたときに自分が思い描くビジョンやルックとは多少のズレがあることは覚悟していました。でも実際に撮影してみると、それぞれの素材がちゃんとなじんでいて違和感がなかったんですよ。だからそこは僕の力量ではなく、各セクションがそれぞれ本当によいものを上げてくださった結果ですね。
――美術も印象的な作品ですが、ロケハンはされているのですか。
藤井 ええ。オフィシャルでも行きましたし、制作だけだったり、個人的に行ったりもしました。5、6回は行っていると思います。
――ロケハンの目的は意思統一をするためだったのでしょうか。
藤井 それもありますし、あとは自分のなかの実感ですね。登場人物の家は北杜市のどこにあるか? 学校との位置関係は? 通学のルートは? ほかにも太陽の傾きや河の流れの向きなど、細かなことでも作品にとっては致命傷になるので、監督としてちゃんと把握しておきたかったんです。当然、この作品に参加するすべてのスタッフが現地を熟知しているわけではないので、制作を進めるうえでどうしてもズレが生じます。そういった部分をしっかり軌道修正していく必要があったので、ロケハンを重ねて実感を深めていきました。
■カブとクラシック音楽の共通点
――音楽についてもおうかがいしたいです。ノンモン(無音)が非常に多いですよね。
藤井 最近、アニメや映画、ドラマを見てると、わかりやすく音楽が付いている印象があるんです。楽しいときには明るい音が、悲しいときには寂しい音が鳴る。それはそれで作品によっては正しい演出ですが、役者の芝居に隠れて音楽の印象があまり残らないのが気になっていて……。
デヴィッド・フィンチャー監督の「セブン」という映画で印象に残っている音楽があるんです。曲はバッハの「G線上のアリア」なのですが、図書館のシーンで守衛がレコードを流し始めると、そのまま音楽に乗せて時間経過の点描が紡がれていく。音楽と映像がどちらも印象的で、ちゃんと演出の両輪になっていると感じたんです。そのときの記憶がやけに鮮明で、こういう演出をいつかどこかでやりたいなと思っていました。
――それで今回はそんな音楽ラインを意識されたと。選曲に関してはいかがでしょうか。
藤井 原作小説を初めて読んだとき、クラシックがハマりそうだなと考えていました。小説や脚本を読んでいると何曲かは自然と頭に流れてくることもあったので、脚本開発と平行して選曲も進めていきました。
――だからご自身で曲付けもされているんですね。
藤井 はい。それと、今回は題材がスーパーカブじゃないですか。誰もが知っている超メジャープロダクツで、個人的には人類史が続く限り残るものだと思っているんです。そういう世代を超えて残り続けるものを描く作品において、ふさわしい音楽はなんだろうと考えたときに、100年近くの時を超えたいまも演奏され続けているクラシック音楽なら、作品に奥行きを与えてくれる気がしたんですね。
――ドビュッシーが多いですね。
藤井 それは好みですけど(笑)。サティ、リスト、ショパンも使ってます。なるべく聴きなじみのあるもので、かつ基本的にピアノの独奏曲でセレクトしました。
――感情が変化するアタック音などにピアノを使ってもいますね。
藤井 ええ。クラシックとの親和性も高いし、作品のテイストとも合うと考えていたので。音楽の打ち合わせの際にその意図を説明させてもらったところ、クラシック曲と同じように実際のピアノの鍵盤を叩いて収録していただけて、結果とても贅沢なタッチ音になりました。
――今回、クラシック以外の音楽は石川智久さんとZAQさんが担当されていますが、各話につき使用曲が極端に少ない気がします。
藤井 もともとキャラクターの感情に合わせて劇伴を細かく当てていくというよりは、シーンの空気感や雰囲気に合わせて大きな流れのなかで音楽を配置していきたいと考えていました。ただ、クラシック曲だけでトータル15~16曲くらいあって、その時点で新たに作曲できる数が減ったので、全体の調整には少し苦心もありましたね。
たぶん作品を見ていて「ここに音楽が乗ってもいいのにな」と思う場所も視聴者側で出てくると思います。でも、それはそれで別にいいとも思っています。ここは絶対必要だと感じるところに音楽を乗せたかった。“なんとなく寂しいから乗せておこう”みたいな音楽の使い方はしたくなかったんです。
――それにしても、本当に被りがほとんど見当たらないので、音楽については非常に贅沢な印象がありました。
藤井 一回しか使ってない曲もけっこうありまして……。石川さんやZAQさんには「あれ? あの曲はいつ流れるのかな?」と心配をおかけしてしまうかも……。
■彼女たちがそこにいる
――演出面、芝居面、音楽面とお話をうかがってきましたが、この作品で監督が描きたかったものはなんだったのでしょうか。
藤井 先程から何度か出ていますが、端的に言えば「空気感」ですかね。原作を読んだときにいろんな方向性の演出ができる作品だなと思ったんですよ。ぱっと思いつくだけでも3つあって。
ひとつは所謂「キャラもの」にして、小熊のセリフを増やしつつキャラの掛け合いで見せる。ふたつめは、カブを主役にして「バイク・メカもの」としてストイックに描く。最後は、この作品の舞台である北杜市とそこで暮らす彼女たちの世界を描く。僕はいちばん最後の方法でこの作品を演出したいと思ったんです。キャラクターに寄り添いすぎず、少し離れた場所から彼女たちを見つめているような。なのでキャラクターとカメラの距離感や構図には注意を払っています。
――カメラワークでも、そのあたりを意識されているのですね。
藤井 はい。くわえて、「カメラが置けない場所にはカメラを置かない」ことも意識しています。アニメって、どこにでもカメラを置けるんですよ。芝居を見せるため、キャラクターの表情を拾うため……そのために描き手の都合で壁をぶち抜くことも地面に潜ることもできます。でも、それはやりたくない。その空間のなかで最良なカメラ位置はどこか探るべきだし、その結果としてキャラクターの表情がよく見えないのであれば、それはそれでいいと考えています。
――それはなぜなのですか。
藤井 彼女たちがそこにいる、その実在感が絶対に必要だからです。その世界を形作るための演出上のルールがないと、なんでもありの浮ついた画面になってしまう。ロケでもセットでも実際にカメラが置けて、かつ画面が決まる場所ってそう多くはないんです。小熊の部屋のどこにカメラを置くべきか、学校の廊下や教室ならどこだろう? と探る。そんなある意味では不便な演出上の制約は、アニメという嘘の世界のなかに実在感というリアリティを与えてくれる根拠になります。これは題材がファンタジーであろうと、舞台が宇宙空間であろうと変わりません。彼女たちがそこにいる。その世界で生きているという実在感、それが何よりも大事だと思っているんですね。
インタビュー後編はこちら
●その他の『スーパーカブ』インタビューはこちら
https://st-kai.jp/works/supercub/
●公式サイト
https://supercub-anime.com/