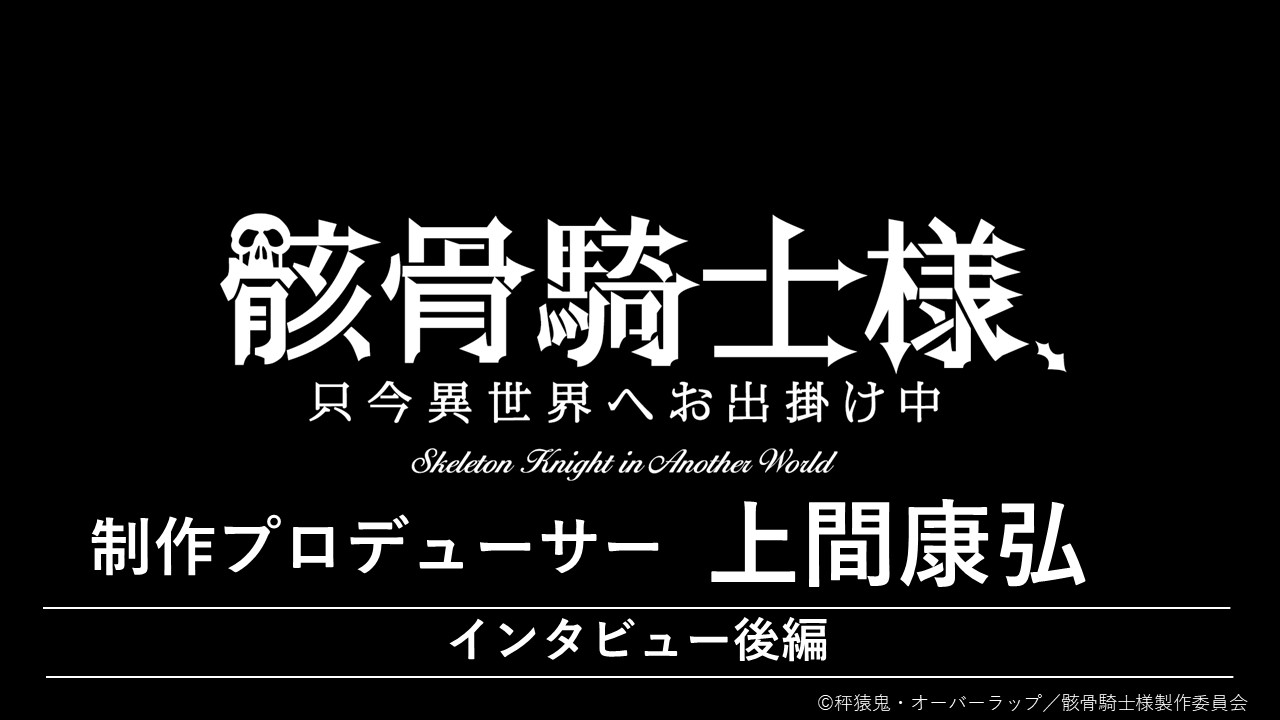『スーパーカブ』 根元歳三(シリーズ構成・脚本)インタビュー【前編】

『スーパーカブ』 根元歳三(シリーズ構成・脚本)インタビュー【前編】
両親も友達も趣味もない、「ないないの女の子」小熊。そんな彼女の単調な生活は、ふと見かけた中古のカブを買ったことで、少しずつ変わり始める――。
現在放送中の角川スニーカー文庫にて刊行中のライトノベル原作作品『スーパーカブ』。
第3回となる本取材では、シリーズ構成・脚本を務める根元歳三に、作品を形作るにあたって心がけたことを中心にお話をうかがった。前後編でお届けする。
2021年4月29日(木)
■ミニシアターが似合う作品に
――本作に参加された経緯からお聞かせいただけますか。
根元 当時は戦闘シーンが多い作品への参加が続いていたんですよね。そういったものももちろん楽しくあったのですが、さすがに何作も続くと「そろそろ戦場を離れたい……」といった気分になって(笑)。戦いのない優しい作品がやりたいなと思っていたおりに、この作品を紹介していただいたんです。実際に読んだうえで、即決させていただきました。
――では、優しい作品性に惹かれたのですね。
根元 ええ。原作を読んでみると、日常をとても丁寧に描いているなと感じて。自分はSFや特撮もの、アクションものも好きですが、ミニシアター系やヨーロッパ映画、古い邦画も好きだったんです。それに近い匂いをこの原作から感じました。自分の「もうひとつの趣味性」と言える資質を活かせるのでは、とも思いましたし、そこが魅力的でした。
――そういう作品を制作することに憧れがあったと。
根元 若いころは典型的な映画青年だったんです(笑)。アニメよりも実写が好きで、映画監督になりたくて、そういう学校に行き、仲間と自主制作映画を撮っていたりもしました。
――(監督ではなく)脚本家になられたのはどういった理由だったのでしょうか。
根元 当時は監督もやりましたし、恥ずかしながら演技もしましたが、自分には向いてないなと。結局は、脚本が楽しくて、引き籠って一人で作業するのが性に合っていたんですね(笑)。そして、そのころに、このインタビューシリーズで監督の藤井(俊郎)さんも名前を出されていたジム・ジャームッシュなんかも良く見ていたんです。
――なるほど。そういった原体験もあったんですね。
根元 東京に出てきてからは、渋谷や恵比寿の単館系作品を良く見ていました……でも、プロになってアニメの仕事をしはじめると、SFや特撮、アクションといった趣味性は発揮できたのですが、もう一方はあまり出せないままで……。
――ご経歴を拝見しても、この作品に近いものはあまりないように見えます。
根元 そうなんです。そのなかで、企画開始当初の顔合わせでプロデューサーの伊藤(敦)さんが、「ミニシアターが似合う作品にしたい」とおっしゃったんです。そのものズバリで言われて、自分としてはそのテイストで行けるんだと。ですから、これまでアニメで培ってきた方法論は一度忘れて取り組もうと思いました。
――実作業として根元さんが最初に行うのは、シリーズ構成を書かれることだと思うのですが、どのようなことを考えられましたか。
根元 藤井さんと相談するための簡単な構成を書きました。A4の紙で2枚くらい、「第1話はここからここ」といった範囲を決めて、各話につき1テーマを定めていったんです。第1話はカブとの出会い。第2話は礼子と寄り道。第3話はいろんなものが集まってくると。それで終わりです。
――では構成表というよりは、メモを書いたわけですね。その方式は珍しいのではないですか。
根元 他の方がどうかは分かりませんが……自分は本来細かく書く方なので、こういったやり方は初めてでした。それとこれも初めての経験ですが、プロットを書いてないんですよ。
――通常、脚本の前にプロットを書くことで、各話の流れを共有しますよね。
根元 空気感が大事な作品だという認識はあったんです。ただ、そこをプロットでは表現できないなと。無理やり書いてみても、監督がジャッジできないと思ったので「いきなり脚本でやらせてください」と。スケジュールに余裕もありましたしね。
――監督のイメージと相違があったとしても、書き直す時間があったと。
根元 ええ。ただ保険の意味も込めて、完全な初稿というよりは少しラフなかたちで検討稿として提出したんですよ。そこからシナリオは推敲していきました。
――しかし、脚本を拝見してみると、どの話数もほとんど稿を重ねられていませんね。最大で3稿までのようですから、決定稿に至るまでが短いように思えます。
根元 メモの段階で、1テーマを書いていたのが効果的だったのだと思います。一行で説明できるぐらいの短さで、端的に核となる部分を共有できていたのかなと。
――脚本を書くにあたって、監督とお話したことはありますか。
根元 最初に監督からいただいたのは「小熊のラブストーリー」ともいえるということです。
――ラブストーリーですか。そうは思えないのですが、誰と誰のでしょうか。
根元 小熊とカブです。「ガールミーツカブ。そういう側面を感じられてもいいのでは」と。
――なるほど(笑)。たとえばどういったところにその視点は反映されているのですか。
根元 第1話で、ベッドのなかの小熊が悩むじゃないですか。で、カブがポンと映るのですが、あれなどは(カブが)男の子のつもりで僕は書いているんです。そして、好きな女の子に会いたいなと思っている。小熊は小熊で「カブに会いにいきたい」という空気を出しているんです。
つまり、ときどき入るカブのカットは、「小熊が好きなカブくん」、もしくは「小熊のことを好きなカブくん」のつもりでした。まぁ、でも、書いているうちに友情で落ち着いた気もしていますが。
――作品の形式面で、監督と最初に定めたことなどありましたか。
根元 「冒頭と終わり以外の、劇中モノローグはやめたい」と。これは当時よく監督と話していたNHKの朝ドラ「ひよっこ」の形式ですね。内容的にも影響を受けています。朝ドラって「何か大きな目標や夢をもった女性」を取り上げることが多いじゃないですか。でも、「ひよっこ」は町の小さな洋食屋のウェイトレスの女性が主人公で、何か大きなものを目指すわけではないんですね。そこがいいなと。
――立身出世ではないのですね。
根元 多くを望まない感じ。少しずつの成長……いや、成長ですらないかもしれない。それぐらいの感じが、『スーパーカブ』に合っているのではと思って参考にしていました。
ほかに監督と話したのは、アニメ的と言うか、説明的な独り言、たとえば「鉛筆どこ行ったかな、あ、あった」といったものはやめておこうと。
――では、その場合どういったセリフ回しになるのでしょう。
根元 たとえば鉛筆を探す動作があって「ううん……、あった」はOK、「どこ行ったかな」まではNGとか。これは、アニメの場合、ある種「保険」という意味もあると思うんです。ながら見をしている人もいるでしょうから(セリフで)補強しておこうということですね。ただ、その方法だとミニシアター系の映画にはならないだろうと。暗闇のなかで集中して見る想定でお芝居もさせたかったんです。
――たしかに、映画館は入ったら、よほどでないと席を立ちませんしね。
根元 ええ。ただ「いまのテレビアニメでその方向性は難しいかもしれない」とは思っていました。ながら見が当たり前になっているこのご時世ですから、どう受け入れられるか不安もありましたね。
そうだ。いまの「セリフを言わせ過ぎない」お話と関連のあるところでいうと、小熊と礼子はあまりお互いのことを名前で呼ばないんですよ。……いや、じつはそもそもシリーズの前半で、小熊は誰からも名前で呼ばれていないんです。
――言われてみればそうですね。それもかなり珍しい気がします。
根元 そもそも原作でもそうなんですけどね。人間って友達と二人っきりのときに、わざわざ相手の名前を呼ばないじゃないですか。「おい」「なんだよ」って。そこは二人の空気感で表現する。それが前提ですので、第2話で悩んだんです。小熊が礼子と出会って、彼女のことをモノローグで語るじゃないですか。あそこで「彼女の名前は確か……礼子」と音に出して言ったら空気感が変わってしまうなと思ったんです。だからあそこはサブタイトルで出すことで、セリフにしないことを選択しました。
――脚本を拝見したのですが、文字数が200字換算で60枚前後と少ないですよね。70枚から80枚のあいだぐらいが通例だと思うのですが。
根元 昨今のアニメから見ると少ないですね。そこの不安はありました。間を大切にすることは、ミニシアター系の話からの派生で共通事項としてあったんです。とはいえ、実際うまくいくのかなと。ただ、アフレコの段階で見たらこの間はいいなと思えたので、「あの枚数でよかったんだな」と思いました。
――各話の枚数が少ないこともあってか、原作の切り取り方も短い範囲であるように思います。第1話は原作の冒頭だけで構成していらっしゃいますね。
根元 今回、この取材をお受けするにあたって読み返したのですが、映像になっているのは原作第1巻でいうと実質23ページ分なんですよ。
――それは相当短いのではないですか。
根元 ライトノベル原作で、自分は今まで経験ありませんでしたね。でも、「これしかないよな」と。
――その23ページ分をAパートにしてしまうこともできるのでは。
根元 いや、たしかにその手もあるのですが、ここまでをAパートで終わらせてしまうと、この作品らしさが伝わらないと思ったんです。
――その考えは、やはりミニシアター系の指針に沿ったものでもあったのですか。
根元 というか、実写の映画ならあるはずの所作や芝居は削らないでおこうと思ったんです。たとえば、職員室に入るシーンがあるとすると、アニメだと職員室のプレートの絵に「失礼します」と言う声が被って、次のカットではもう入っている。でも、実写だったら、普通にがらっと扉を開くところを撮りますよね。まぁ、それは、扉を開ける動作をアニメーションで描くのが大変だということもあるのですが。今回、検討稿や初稿ではそういった部分もあえて遠慮しないで書きました。そのうえで「さすがにこれは(アニメーションの労力的に)難しいです」と藤井さんにご指摘いただいてから直そうと。
――そうなると、地の文ばかりになっていくと思うのですが、セリフを入れないことに対する怖さはなかったのですか。
根元 じつはそれほどなくて。自分が若いころ見ていた映画って、こんなのいっぱいあったよなと。そこが根拠でした。むしろアニメの脚本を書くようになって、意識してセリフを多くする癖がついたんです。「アニメはセリフを入れておかないとダメなんだ。そういうものなんだ」と。でも今回は、その二十何年間培ってきたものを忘れて、ただの映画青年の自分に戻ろうと。
――これぐらい原作の範囲を短く映像化していくのであれば、アニメ全体で描かれる範囲もそれほど長くないわけですね。
根元 そうなりますね。ただ、この手の原作物だと「後半に登場する人物を早めに出してほしい」だったり、「テンポ感をあげてくれ」とリクエストされることもあるんですよ。それはやりたくなかったんですよね。
――ミニシアター系らしい作品のムードが変わってしまうから。
根元 それもあるのですが……。先ほど1話につきひとテーマとお話したように、1話にひとつ小熊が新しいものと出会っていく話なんです。なのに、いきなり三つも四つも出てくると、それは小熊の世界が広がっていくスピードと合わないだろうと。小熊のペースというか、小熊に合ったスピードで成長させてあげたかったんです。だから、原作を描く範囲も無理して長くはしませんでした。
――なるほど。小説からの実際に脚本へと落とし込むにあたって、セリフの取捨選択はどのようにされていたんですか。
根元 セリフの取捨選択か……どうだったかな。追加した部分もあって、そこに関しては(原作の)トネ(・コーケン)先生から、「こういうセリフを使ってほしい」といったサンプルはいただいていたので、それを組み込んでいたりしています。すみません、この点についてはあまり覚えていないですね……。
――ここからは、脚本を拝見していて驚かされたポイントを中心にお聞かせください。セリフにおける三点リーダーが非常に多い作品ですね。
根元 たしかに。小熊は口数の多いキャラではないので、ただそこにいるだけではなくて、「何か思うところがあります」というのを(コンテマンに)伝えるために今回は多用しました。
――三点リーダーはまだほかの脚本でもよく見るのですが、セリフ途中がカッコになっている箇所が頻出しますね。
根元 ああ。そうですね。「どういう(ことなの……)」といったことですよね。
――これはこのカッコの部分は音としては言わないけど、あえて明示しているわけですね。
根元 それも普段ならあまりやらないことですね。日常会話って最後までしっかり言わないじゃないですか。「あれって……」「あれね、こっちだよ」ぐらいだと思うんです。そういった雰囲気を出したかったんです。
とはいえ、全ての話数のコンテを藤井さんが切るわけではないので、ガイドとしてカッコ付きで続きを示したんですね。その次に続くはずなのはこういう言葉ですと。今回こういう作品だからこそ、そう提案したのを覚えています。
――少し話が飛びますが、実際に映像になったものと、その時にイメージされていたものは割と近かったのでしょうか。
根元 近……くはないでしょうね(苦笑)。想像以上に実写でした。「そうはいっても」ですよ。びっくりしました。
――それはアフレコの段階でそう思われた。
根元 いえ、オンエアを見てからです。アフレコのときは、色までは付いていなかったのですが、色あいがアニメじゃないんですよね。ああ、なるほどと。
それと、音楽ですね。使い方がここまでイメージできていませんでした。既存の曲を使う話は脚本打ち合わせのときでもしていたんです。小熊がラジオを聞いているので、そこでジャズのような既存の曲を流すかもといった話がありました。
――そのときは、明確にクラシックではなかったのですね。
根元 ただ、音楽シーンに近いものはほしいと。だからバイクで走っているだけだったり、風景だけといった、セリフのない、音楽がかかるであろうシーンは書きました。
――脚本のなかに「ここから音楽がかかる」と明示しているところもありますね。
根元 それは……書いちゃったんですね(笑)。自分の意志だったのか、藤井さんに「書いておいてください」と言われたのかは失念しましたが。
――根元さんは音楽シーンが多い作品にも参加されていますが、このようなかたちで明示されたことは……。
根元 ないと思いますけど、どうでしょう? あったとしても、やはり特別なケースだと思います。若いころ、先輩ライターさんに「そういうものは演出の範疇だから脚本では書くな」と注意をされました。ただ、今回は特殊な演出をする作品だという意識はあったので、あえて入れ込んでみたんだと思います。
――さまざまな挑戦をこの作品で行っているのですね。
根元 というよりも、知らないうちに、身に付いてしまったものがあったんだなと感じました。「このほうが通りがいいから」と、脚本打ち合わせの場でも、視聴者の反応的にも、そんな考えでいたと思います。でも「学生のころはこういう書き方をしていなかったな」とは、うっすら思っていて。それは成長でもあったのですが、どこか居心地の悪さも感じていたのかもしれません。
インタビュー後編はこちら
●その他の『スーパーカブ』インタビューはこちら
https://st-kai.jp/works/supercub/
●公式サイト
https://supercub-anime.com/