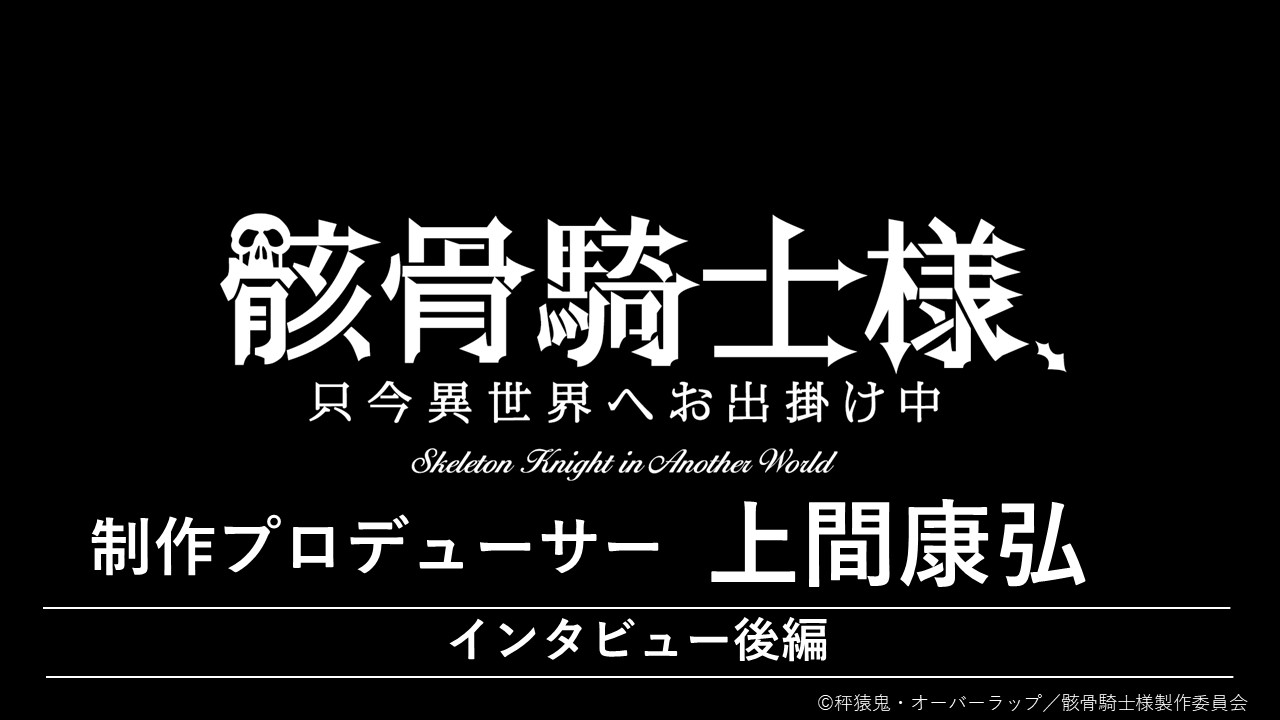『スーパーカブ』 藤井俊郎(監督)インタビュー【後編】

『スーパーカブ』 藤井俊郎(監督)インタビュー【後編】
両親も友達も趣味もない、「ないないの女の子」小熊。そんな彼女の単調な生活は、ふと見かけた中古のカブを買ったことで、少しずつ変わり始める――。
現在放送中の角川スニーカー文庫にて刊行中のライトノベル原作作品『スーパーカブ』。
インタビュー後編では、本作の監督を務める藤井俊郎に、引き続き作品の魅力や特徴を聞いた。
2021年4月15日(木)
インタビュー前編はこちら
■キャラクターではなく、人間として
――放送が開始されました。踏まえてお話をうかがわせてください。まずは何より、小熊の笑顔が印象的でした。
藤井 小熊はもともと無口で無表情なキャラなので、その分、笑った時の印象がより際立つのかもしれませんね。演出や作画のチームにも「小熊は周りに人がいるときは感情を表に出さないけど、ひとりだったり、カブに乗っているときは、喜怒哀楽が表情に出てもいいです」と話していました。
――PVでは、若干表情の変化に乏しい印象だったので驚かされました。
藤井 他人と積極的にかかわりを持ちたいという子ではないので、普段から愛想を振りまくことがないんです。でもカブに乗って、心が動いたときはつい頬が緩んでしまう。そういう“人間らしさ”もしっかりと描いてあげたかった。むしろ、その普段見せない表情が出たときに「かわいらしいな」と思ってもらえたらいいなと。
それと、セリフの少なさも一役買っていると思います。淡々とした日常のなかだからこそ、感情が動いているところをしっかり描いてあげると、その表情は印象に残るんですよね。
――今後小熊が見せてくれる様々な一面にも期待したいです。
藤井 第2話以降は、礼子との絡みもあるのでさらにおもしろい面も出てきます。今まで友達もいなかったし、会話らしい会話もしてこなかったので、いろいろ不器用だったり、他人との距離感がちょっとズレてたり。
――視聴者のなかには違和感を持つ方もいるかもしれないですね。
藤井 それはそれでいいんです。普段の生活でも初対面では「なんだコイツ?」って思ったけど、仲良くなってみると実はいい奴だった、みたいな経験って誰にでもあると思うんです(笑)。だから、それはマイナスではなくキャラクターが持つ”人間らしさ”のひとつだなと思っているんです。
――もうひとつ、感情表現についてなのですが、小熊がカブを動かす際、くすんだ風景から、映像が色づいていくのが印象的でした。
藤井 色彩の演出については珍しい表現ではないし、手法としては古典的ですが、直接的に影響を受けた作品はトム・フォード監督の映画「シングルマン」です。かすかに心が動くとき、ほのかに世界が色づいていく。そうやって、主人公の感情表現をしていたんですよね。派手じゃないけど、すごく効く演出だなと思って。で、『18if』で試したんです。そのときの手応えがあったので今回はシリーズ全体を通して演出に落とし込みたいなと考えていました。
――ただ、それをするためには、その瞬間に行き着くまでに全体の色を抜かないといけないですよね。
藤井 そうです。ただ、単純に彩度を抜くだけだと中途半端な画面になってしまうので、ブリーチバイパスというか、銀残し(※1)みたいなルックにしたかったんですよ。
(※1)映画フィルムの現像手法のひとつ。プリントの工程で行われる銀を取り除く処理を省くことで、暗部が暗くなり、ハイコントラスト気味で少しくすんだ色味になる。
――そういう色味がお好きだったのですか。
藤井 アニメ、実写、写真問わず、色鮮やかなものよりも少しくすんでる方が好みではあります。ただ、この表現が『スーパーカブ』に持ち込めそうだなと思ったのは、やっぱり小熊の存在があったからです。家庭環境が他人とは違う、感情表現もあまりない。ある意味、色鮮やかではない世界で生きている子ですよね。けど、カブに出会って少しづつ環境が変わる。世界が少しだけ違って見える。そこでふわっと色づくからこそ、鮮やかな色味が活きてくる。
――先ほどお話された、淡々としているから笑顔が際立つ、に似たお話ですね。
藤井 はい。そういう設計をしています。ただ、この演出を目立たせたいわけではなくて。小熊はカブを手に入れたけど、それによって彼女の世界が一変したわけじゃない。その変化は本当に少しずつなんです。だからほんの少し色づくようにしています。これは、全編通していくつかの場面でやっていますね。
――なるほど。それはしかし、実写映画で行われるカラーグレーディングの領域に入り込んでいないでしょうか。
藤井 そうです。はっきりとグレーディング(※2)をやりたかったんです。アニメ業界ではあまり一般的ではないけど、それこそ作品の世界観を一変させてしまうくらいのパワーを持っている行程なんですよね。
(※2)カラーグレーディングとは、主に実写映画において、映像演出の延長として色を調整すること。シーンやカットごとに調整する場合もあり、藤井監督の発言にはその意味合いがふくまれている。
ただ、いまのTVアニメの現場環境ではなかなか難しい。じゃあ、どう実現するかを考えるわけですが、これも既に『18if』のときに作業工程を構築していたので、『スーパーカブ』用に色彩のフィルターを調整して、撮影チームと手順を共有することで実現していきました。
――カラグレは実写映画の手法だと思うのですが、そこからの発想だったのですか。
藤井 はい。ただ、実写のようにシーンやカットごとに細かく調整する事はアニメではできません。今回は作品全体のトーンと色彩演出のコントロールに限定して持ち込んだイメージです。撮影の行程で使用するAfter Effects(さまざまな分野で広く使用されている映像加工ソフト)の特性、向き不向きは分かっていたので、「これは実現可能、これは不可能」と線引きをして、やれる範囲でやってみようと。
――くすみ気味の映像が続くこともふくめ、思い切った選択だと思います。
藤井 キレイな画面の方が視聴者も見慣れているし、今回のような色味はリスキーだと思います。それでも、こういうやりかたを認めてくださったKADOKAWAの伊藤(敦)プロデューサーには本当に感謝しかありません。
――アニメでこのような手法を採られるのは珍しいですから、スタッフに周知するのにはご苦労があったのではないですか。
藤井 ありましたねぇ(笑)。でも、それは因果応報なんです。僕が「こういう方針でやります」と決めたから発生した苦労なので、完全に自分の責任。スタッフの多くは、カブには乗っていないしロケハンにも行けていない。加えて通常の様式とは違ったアニメーションを作りたい。そんな状態では自分が思い描いていることが、1から100まで相手に伝わるなんてことはまずないので、そのことが原因で作業が滞ってもそれはスタッフの皆さんのせいではない。
だから、とにかく自分自身も手を動かしながら、言葉を尽くすところは尽くして、作品の方向性を提示し続けるしかなかったですね。確かに苦労はありましたが、作品の”芯”のようなものは共有できたので、そのかいはあったと思います。
――小熊がカブを動かす際に、もうひとつ印象的だったのが音です。エンジン音が非常にリアルに聞こえました。
藤井 「カブの音は最重要項目」という共通認識が現場にありました。なので、実機を使ってリアルな音を収録するべく、トネ先生が所有するカブをお借りしました。しかも、トネ先生が自ら軽バンに積んで搬入するという(笑)。さらに音響効果の倉橋(裕宗)さんみずからも小熊と同型のカブを用意されて、作品内の描写に必要なありとあらゆる音を収録してくださいました。
――ああ、あれは本物の音だったのですね。
藤井 エンジン音も、ギヤチェンジの音も、何もかもが本物です。これは、実際のカブオーナーやバイクファンが聞いても満足してもらえるんじゃないかなと。
――カブに乗ったときの風切り音など、効果音の付け方にもこだわりを感じました。
藤井 カブに乗っているときと停まっているときでは、当然ながら風切り音もエンジンの音も使い分けています。この「実際に乗っているときのような感覚」を音で再現するには、リアルに乗車経験がないと難しいと思うんですが、今回は実際にカブオーナーでもある倉橋さんが音響効果を担当しているし、音も本物です。そこから導きだされたリアリティはこの作品の柱のひとつになっていると思います。
――なるほど。いっぽうでカブ以外の音……たとえば鳥の声などの環境音、炊飯器を開ける生活音も印象的でした。
藤井 「過剰に音楽を乗せない。派手な芝居やコミカルな演出も避けて淡々とした世界観で作っていく」という方針にした時点で、カブはもちろん日常生活の音や環境音がとても重要になるということはわかっていました。なので、音響効果チームと演出プランを共有して、そこから必要になる効果音について話し合いました。効果音の準備や収録に関しては一任してダビング(音楽や効果音などについて、確認、編集していく作業)当日に確認したのですが、第1話冒頭の生活音のリアリティは本当に見事でした。作品全体を通して非常に素晴しい”音”を演出してくださっています。
――こういった生々しい音を作るのは、やはり難しいものなのでしょうか。
藤井 ええ。普段は意識しないですけど、人間が生活しているだけで実際にはいろんな音が発生していますよね。それは当たり前のことですが、その「当たり前」をアニメの世界で再構築するのは非常に難しいんです。
――具体的にはどういうことでしょう。
藤井 たとえば、道を歩いている自分の足音を意識している人はそういませんが、作品世界のなかでそれらの音がなかった場合、強烈な違和感が発生するんです。普段の生活で無意識に聞き流している音を、アニメでは一から意識的に拾い上げて、さらに違和感のないように配置しないといけない。ましてや、今回は音楽も少ないのでごまかしも効かないし、さらに記号的な効果音を排した作品なので、そのほとんどが生音です。
――なるほど。サンプリング音源ではなく、生音であることを重視されていたのですね。
藤井 非常に難しい要求でしたが、いつも要求以上の仕事で応えてくださり、職人技を間近で見せてもらった印象です。
――音に関連するお話を続けさせてください。キャストの芝居についてはどのような方針だったのでしょうか。
藤井 「声を作らなくていいので、少し抑えたリアリティのある芝居で」とお願いしました。キャラクターを演じるというよりは、普段の自分の延長線上にそれぞれのキャラがいる感じというか。七瀬(彩夏)さんや日岡(なつみ)さんはすでに声優としての実績もあったし、夜道(雪)さんも当時は新人ではあったものの、これだけアニメが放送されている世の中なので、聞き覚えのある芝居に引っ張られるかとも思っていたのですが、3人とも最初のアフレコの時点で完成形が見えていた印象ですね。音響監督の矢野(さとし)さんとも作品の世界観や演出志向を共有していたので、キャストへの演技指導はお任せして、自分は彼女たちの芝居と『スーパーカブ』の世界感のズレをチューニングすることに注力していました。
――アフレコ中に印象に残った出来事などありましたか。
藤井 コロナ禍での収録でしたが、大きなトラブルもなく平和でアットホームな現場だったと思います。
ただ、最初のアフレコのときだったかな。収録のテスト中に規則的なノイズが聞こえて、「このノイズ、なんですか?」と聞いたら「夜道さんの心音です」と。驚きとともにキャスト、スタッフ一同で爆笑。夜道さんは恥ずかしそうにしていましたけど、これは彼女にとって”声優初主演”と同じくらい価値のある”宝”になっただろうなと。だって、こんな愛らしい鉄板エピソードを持っている声優はそういないでしょうからね(笑)。
――七瀬さんについてはいかがでしょう。
藤井 礼子の特徴である「カブうんちく」に少し苦労していたかな? まあ、早口で長文な上にカタカナの専門用語がいっぱい飛び出すので無理もないんですけど(笑)。
――そうでしょうね(笑)。
藤井 いつも前向きで休憩中にも一生懸命練習してましたね。あと、専門用語の意味やイントネーションをバイカーでもある夜道さんに確認したりしていて、作品内のふたりと同じくよいコンビになっているのがすごく微笑ましかったです。
――日岡さんについてもお聞かせいただけますか。
藤井 「恵庭 椎」と同じく「明確なビジョンとプロ意識」を持っているなぁと。アフレコ中に印象的だったのが、こちらでOKを出した芝居に対して「今の芝居、もう一回やらせてください」と自ら再トライしたことがあったんですよね。その熱意や自分のなかの芝居を追求する姿勢は夜道さんや七瀬さんにもいい影響を与えていたし、そんな意識を持った彼女がいるだけで現場の空気が締まるというか、とても心強い存在でしたね。
――第1話ではカメラワークも印象的でした。同ポ(カメラポジションが同じカット)が多用されていましたね。
藤井 そうですね。”定点観測のカメラが切り取っている風景”のような見せ方がこの作品にとって大事だと思っていたので。
――それはどうしてなのでしょう。
藤井 原作小説の世界観を丁寧に描くためには、どうしても春夏秋冬が必要になるんです。そのときに、いつもの場所を同じ構図で見せることで季節の変化をより明確に打ち出すことができるんです。
――あるときは雪が降っていて、あるときは強い日差しが照っている、といったことですか。
藤井 そうです。それにこの世界に流れている空気感を再現するには、街に住む人たちが生活している時間帯の再現も必要ですから。朝、昼、夕方、夜。同ポであればその変化も明確にできるので。
あとは、単純に美術の労力を減らすことも念頭に入れました。
――同じ場所であれば一から描かなくていいですからね。
藤井 はい。美術を大切にしている作品だからこそ、季節感、時間帯の変化もしっかり描きたい。なので美術側の労力バランスも考慮して、各話数のコンテマンには積極的に同ポを使って欲しいとお願いしていました。
――なるほど。同ポであれば、それ以前の話数からレイアウトも流用できますね。
藤井 と思っていたのですが……いろんな演出修正が入ったり、上手く共有のレイアウトが渡っていなかったりもして(笑)。「これ同ポでいいのに!」、「フレーム変わっちゃってるよ!」みたいなことはありましたね。最終的に、労力はあまり変わらなかったかも……(苦笑)。でも絵については「あの場所に、今日は雪が降っている」とわかりやすく、情感も込めて描写できていると思います。
――第1話でいうと、サブタイトルが出るまでのアバンシーンと、エンディングが掛かっているシーンとで、小熊はほぼ同じ構図で同じ行動をしていますね。これも同ポ的表現だと思うのですが。
藤井 毎日を同じようなルーティーンで消化していた彼女の日常が、カブの存在をきっかけにどう変わったのか。導入でもありますし、その対比を明確にしたかったので、あえて同ポ演出でやっています。また、この第1話のような演出の志向は全編に通してありますね。
――小熊が礼子、椎とどうかかわっていくのか。また、その関係性の変化も気になるのですが。
藤井 まだ放送がはじまったばかりなので多くは語れませんが、小熊と礼子はあくまで”同じカブ乗り”という関係性で信頼が深まっていきます。だから”友だち”という温度感とも少し違うんですよね。そこに、椎という新たな人物が加わることで、3人の関係性にさまざまな化学変化が起きていきます。
――では、礼子と椎が鍵になるのですね。
藤井 そうですね。ただ、椎については原作準拠で小熊たちとの合流までに若干時間がかかるのですが……(笑)。とはいえ、これまでひとりだった小熊の人間関係は少しずつ、確実に広がっていきます。いっぽうで、その変化に対する彼女たちの思いや感情を誇張したり分かりやすく説明したりはしていません。自分は作品について、人によって解釈が違ってもいいと思っているんです。なので、視聴者のみなさんひとりひとりがそれぞれに感じていただければ。
――関係性や感情面についても、空気感を大事に作られているのですね。
藤井 はい、空気感は大事です。ただ、これまでインタビューを受けておいてなんですけど「これはこういう意図です」と演出家が明言するのは無粋というか、あまり好きじゃないんですよね(笑)。自由に解釈してもらって、むしろ自分とは違う意見に対して「なるほど、そういう見方もできるのか~」とか、好きに話し合って欲しいんですよ。それって純粋に嬉しいし楽しい。そういうのが豊かな作品だとも思うんですね。『スーパーカブ』もそういう作品になっていて欲しいなぁと。
――監督は様々な思惑があって演出をされているのに、実際感じて欲しいのは、制作意図ではなく空気感だった、というのは不思議な感覚がします。
藤井 確かに意図と空気感って真反対なイメージを持たれるかもしれませんね。まあ、いろいろ考えた結果、余白の多い作品にしたかったんですよ(笑)。
●その他の『スーパーカブ』インタビューはこちら
https://st-kai.jp/works/supercub/ ●公式サイト
https://supercub-anime.com/