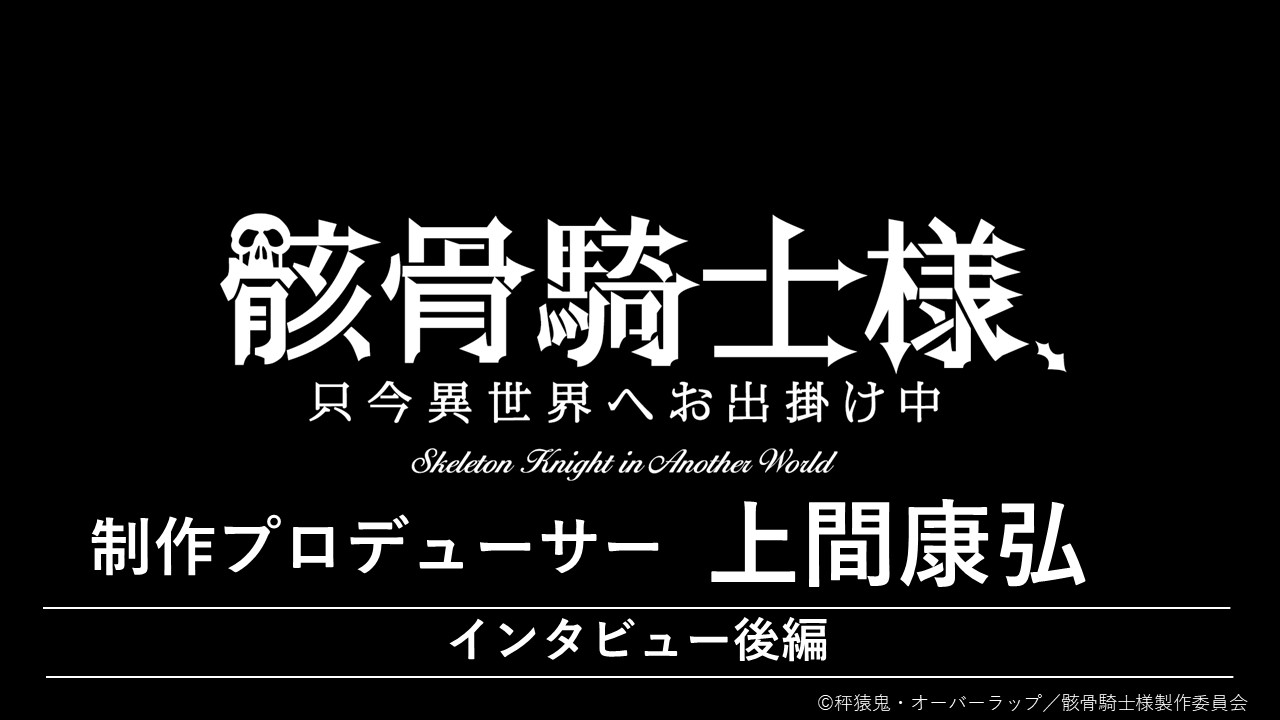『スーパーカブ』 根元歳三(シリーズ構成・脚本)インタビュー【後編】

『スーパーカブ』 根元歳三(シリーズ構成・脚本)インタビュー【後編】
両親も友達も趣味もない、「ないないの女の子」小熊。そんな彼女の単調な生活は、ふと見かけた中古のカブを買ったことで、少しずつ変わり始める――。
現在放送中の角川スニーカー文庫にて刊行中のライトノベル原作作品『スーパーカブ』。
第4回となる本取材では、シリーズ構成・脚本を務める根元歳三に、本作ならではの挑戦について引き続きお話をうかがった。
2021年5月6日(木)
インタビュー前編はこちら
■ただのモブAにならないように
――サブキャラクターのセリフが短いながら印象深いのですが、意識されたことはありますか。
根元 サブキャラクターは原作だとあまりしゃべりません。××は小熊に〇〇と言った……というように地の文で描かれることが多いような気がします。ですが、アニメにすると顔が出てくるので、自然とセリフも多くなるんですよ。そのセリフ回しをどうするか、とても気を付けました。彼らは小熊がカブに乗ることで出会えた人物なんですよね。カブを通じて出会ったものは、道具も景色も人も、すべてを大切に描きたかったんです。
――ただのモブAにならないように。
根元 はい。だけど、個性を付けすぎてもいけなくて。藤井さんに、「このキャラは口癖をつけすぎです。やめてください」と言われたこともありました。
自分としてはこういう年恰好で、こういうバックボーンがあって、だからこういうしゃべり方なんだと考えて口調は作りました。第1話のコンビニで「気をつけて帰れよ」と言うおっちゃんも大切だと思っていましたよ。
――(笑)。
根元 実写だと、ワンシーンしか出てないコンビニの店員でも、気になったりするじゃないですか。あれがなかなかアニメだとできないんですよね。絵で特徴をつけてしまうと、キャラが変に立ってしまうんです。
――なるほど。人間というより、キャラクターになると。
根元 実写だったら、立っているだけでも気になる感じにできる。それは役者さんの存在感や演出で醸し出すことができるんです。アニメでも「こんな小さなキャラクターにこの大物声優を!」と、キャストをあてることがありますが……。
――少しネタっぽくなりがちですからね。
根元 そうですよね。そういった実写に対する羨ましさもあって、こういう書き方をしているんだと思います。
――地の文を拝見すると、とても静かといいますか、落ち着いたイメージが思い浮かびます。テクニック上の秘訣などあるのでしょうか。
根元 まず、ト書きに主観を入れないことですかね。事実だけを書いて、キャラクターの感情を示すような文章はあまり書かないことを意識しました。「小熊がどう思っているか」といったことは最小限度にし、「ズバッと」といった擬音は入れず、「さっそうと」といった派手な言葉は使わず、形容詞も極力省いています。
――うれしい、楽しいといったことですかね。
根元 そういうことです。くわえて、原作のトネ(・コーケン)先生の文体自体が、正直ラノベっぽくないんです。ハードボイルド文学の香りがします。あの淡々と進む感じ。それをできるだけ再現したいわけです。華やかな単語を使ってしまうと、コンテマンさんが「そういう」絵にしてしまうかもしれないので、端正な言葉を心がけたつもりです。
――しかし、そうなると感情表現は難しくなるのでは。
根元 本作の場合、小熊がうれしいときに「わあっ」となることは少ないですよね。ですから、そういったシーンでは、例えば青空の下、カブで走ってもらう。さみしければ、カブが雨に打たれている。セリフや表情以外の手段を総動員していました。
――第2話のラストカットで、小熊がウインカーランプを消しますよね。これは脚本になかったようですが、いまのお話に近い演出であるように思えます。
根元 あれは藤井さんの(コンテ時における)付け足しですね。ラストより前の段階で一回消し忘れをやっているから伏線もあって、コンテを見たときにおもしろいなと思いました。小熊って感情表現が難しいじゃないですか。でも、あそこで忘れちゃうことで、「浮かれ感」の表現ができるんですよ。「淡々としているけど、実は……」と。すごくいい変更でしたね。
――この作品において、もっとも挑戦したといえるシーンはどこになりますか。
根元 第1話のBパートですね。ほぼほぼひとり芝居を、しかも第1話でやる。これは冒険と同時に「こういう作品なのだ」という意思表示でもありました。
――たしかに、前半でシノさんと別れてからは、ずっとひとりですね。
根元 書くときに覚悟を決めましたね。これはやらないとだめだと。
――Bパートまるまる一人芝居は、これまでも経験がないですか。
根元 ないですね。10年くらい前に『赤毛のアン』を見直していたんです。その第1話のBパートが二人芝居なんですよ。それを見て以来、ずっとこんなことがしてみたいと思っていました。
――馬車のうえで、アンがマシュウにずっとおしゃべりをしているところですね。
根元 そこですね。後半の回でも、『赤毛のアン』にインスピレーションを受けた回があるのですが。いつか、あれを……こんなことを言うのもおこがましいのですが、ああいった作品性のものをやりたいと思っていたんです。なぜ二人が話しているだけでおもしろいのか。どうしてこんなに間がもつのか。衝撃的だったんです。
――たしかに本作を全体的にみても、雰囲気は『アン』を想起させるものがありますね。
根元 そこは藤井さんというより、自分のせいかもしれません。
――ほかに具体的な作品で、影響を受けているものはありますか。
根元 あとは小津安二郎の「お茶漬けの味」ですね。ちょっとぎくしゃくした夫婦が、仲直りしてお茶漬けを食べるのがラストシーンなんです。「腹が減った」「何かあがる?」と言って。普通なら次のシーンで食べている絵になるじゃないですか。でも、ふたりが居間から出て、廊下を歩いて、台所に行っておひつを探して、「あったあった飯」なんて言って見つけて。また廊下を歩いて、居間に戻って、座って、おひつのふたを開けて、お茶碗にご飯を入れる。
――過程を全部やっていますね。
根元 そうなんです。「腹が減った」と言ってから、食べるまで時間を切ってないんです。なぜ切らないのかというと、ふたりが仲直りする大事な儀式だからなんじゃないかなと。
だから小熊がカブに乗る場面では、グローブをはめたり、ヘルメットをはめるのは、あえて削らなかったんです。多くの場合、第1話でやったら、第2話からは削ることも多いと思います。でも、それは小熊にとって大切な儀式のはずだから、小熊が大切にしているものは、原則として尺やテンポを言いわけにして削ったりはしない。その大切さがちゃんと伝われば、いい作品になるんじゃないかと。
――なるほど。
根元 藤井さんに会ったときにいちばん最初に話したことがあって、子供のころだと、5,000円のものを買うのは一大事件だよねと。朝からどきどきして、お店に行って、見て、一度は帰ってしまう。でもまた行く。で、また家に帰る。次の日また行って、同じことを繰り返して、1時間くらいしてやっと買う。そういうことってあるよねと。
――なんとなく、その気持ちがわかります(笑)。
根元 そのどきどきは、ちゃんと脚本にして演出すれば、絶対おもしろくなるはずだと思って。
――派手なことを起こして盛り上げるのではなく……。
根元 この子にとっては、それが一大事だということを意識してやりたかった。それは第1話から第12話までこころがけたことでした。だから、切る切らないは……。
そうか……思い出しました。前回のインタビューでお話があって、そのときはちゃんとお応えできませんでしたが、それは、ここなんです。
――ええっと……ああ、セリフのどこを取捨選択したかのお話ですか。
根元 そうです、そうです。だから、自分や視聴者にではなく「小熊たちにとって」大事かどうかが選択のポイントだったんですよね。
――放送が開始されて、いままさに反響が届いているかと思うのですが、いかがですか。
根元 正直、地味な作品になるだろうなと思っていました。いい作品になったとして、果たして多くの人に受け入れてもらえるんだろうかと。打ち合わせの席でもそんな話になったことがありました。この作品は、一見キャッチーではないかもしれない。でも、派手にアレンジするとか、売れ線を狙うための過剰な努力はあまりしたくない。だから、いまのトレンドからは離れてしまうかもしれない。しかし、この原作の良さをアニメにするということは、そういうことではないかと。そうしたら、プロデューサーの伊藤(敦)さんも「それでいいと思います」と。
――それは驚きですね。
根元 よく打合せの帰りに藤井さんと「大丈夫だろうか。本当に見てもらえるんだろうか」と話をしていました。でもこんな作品を作れるチャンスは最初で最後かもしれない、だからやろうと。
――ではあらためて、どうしてある一定の層に、本作が刺さっているのだと思いますか。
根元 どうしてなんだろう。(少し考えて)質問の趣旨と少し違うのかもしれませんが。僕が原作を読んでいちばん感動したのは、第2話の角を曲がるところなんですよ。
――交差点でいつもは曲がらない角を曲がるところですね。
根元 はい。それにすごく感動して。人生を変えるのは大変で、変わりっこない。そう思いがちですけど、角を曲がるだけで変わるのかもしれない。アイドルになれなくても、ヒーローになれなくても、角を曲がるだけの小さな変化で人生を変えられる。そこがちゃんと描かれているから、自分のことのように重ねられるのではないかなと。
――簡単にアイドルにはなれないですしね。
根元 世界を救うヒーローにもなれませんから。でも、いつも曲がらない角を曲がってみることは誰にでもできる。それは自分達にとって「実感できる変化」として感じてもらえているのかもしれません。
――これは自分の物語だと。
根元 そういうことですね。自分の小さい話。でも、「小さいままでもいいじゃないか」ではなく、前向きに、ちゃんと変化している。とても些細で、目に見えないけど、その子にとっては生きるにあたって大事な変化だったりもする。そして、それを積み重ねていく。人生ってそういうものなのかな、と思うんですよ。
●その他の『スーパーカブ』インタビューはこちら
https://st-kai.jp/works/supercub/
https://supercub-anime.com/