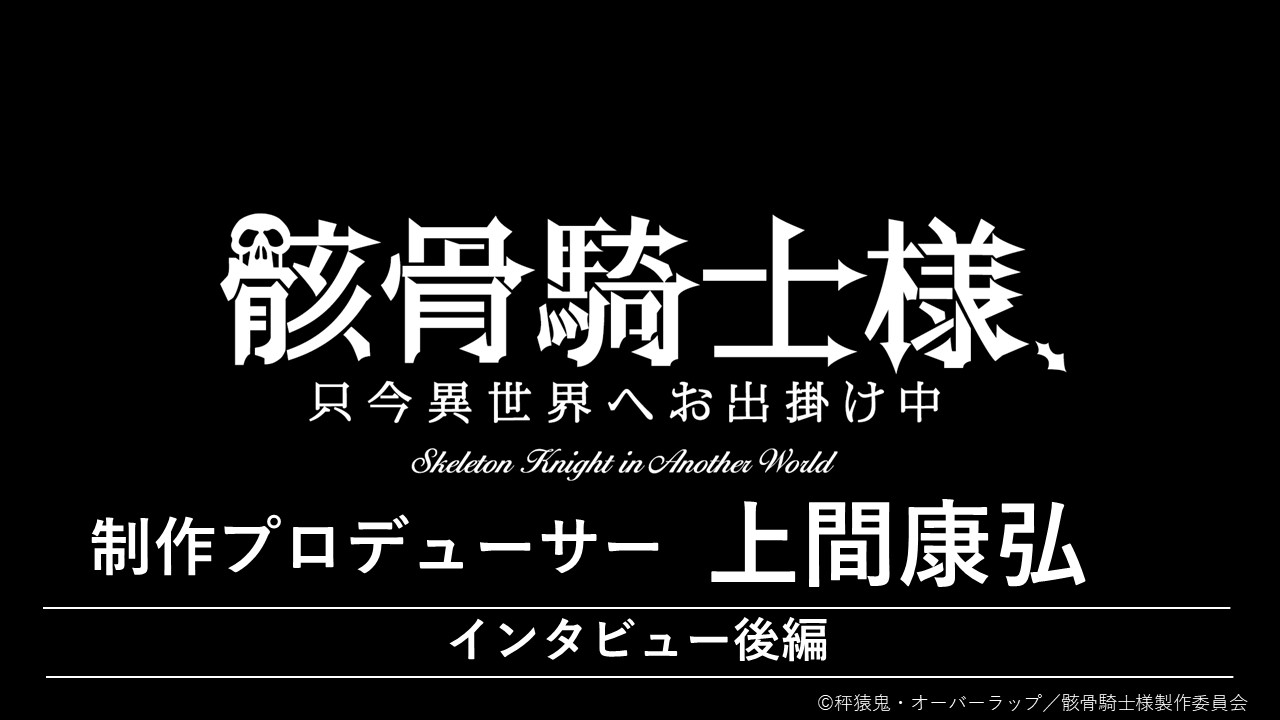『スーパーカブ』 矢野さとし(音響監督)インタビュー

『スーパーカブ』 矢野さとし(音響監督)インタビュー
両親も友達も趣味もない、「ないないの女の子」小熊。そんな彼女の単調な生活は、ふと見かけた中古のカブを買ったことで、少しずつ変わり始める――。
現在放送中の角川スニーカー文庫にて刊行中のライトノベル原作作品『スーパーカブ』。
第8回となる本取材では、藤井俊郎監督と組むのは『18if』以来二回目という、音響監督の矢野さとしにお話をうかがった。
2021年6月17日(木)
■視聴者が気にならない音を
――藤井(俊郎)監督とは以前からのお付き合いになるそうですね。
矢野 はい。『18if』で(ミキサーとして)ご一緒しました。あの作品も静かで、演出法も『スーパーカブ』に近いものがある作品でしたね。セリフでも音楽でも語らず、情景だけで見せていく。度胸がないとできないものづくりだと思いました。ただ、『18if』のときは各話監督制ということもあり、1話だけの演出法でしたが、まさか(『スーパーカブ』では)全話数でその演出法を通すとは……。藤井監督は、大いなる決断をなさったなと思いました。
――そんな静かな作品を手掛けるにあたって、音響面で気をつけたことはありますか。
矢野 日常の環境音をやりすぎない。自然な形で主張せずに積み上げていくのが大事でしたね。目指すところは視聴者が気にならない音なんです。「あそこ、いい音だったよね」なんて残って欲しくはないんですね。その意味ではリアルであることも大事で。効果を頼んだ倉橋(裕宗)くんが、そういった仕事をしてくれる方なので、非常にありがたかったですよね。今回は音楽がないぶん、フォーリー(足音や衣擦れなど、主に生音で収録されるもの)がものすごく重要ですから。
――フォーリーとは、どのように作られるものなのでしょうか。
矢野 映像を観ながら、自分で手足を動かして、歩き、衣擦れ、細かい金具の音など付けていくんです。場合によっては自分でドアをブースに持ち込んで開けてみたり、今回はスーパーカブも自前で用意して音を録っていますし、けっこう大変な仕事ですよね。
――カブの音はやはり本物でなければいけなかったのですか。
矢野 カブの音って日常の中で誰もが聞きますからね。そういった「当たり前」の音に対して手を抜くと、視聴者はすぐに気がつくんです。当たり前の音こそが、何より大事なんですよ。
これは音響だけでなく、アフレコ演出にもいえることで、たとえば「コメリ」のアクセントを現地の表現に合わせたりなんてことも近い話ですね。現地では当たり前のことをしっかり再現しないといけない。
――山梨に方言らしいものはあまりないように思うのですが。
矢野 そうですね。でも、ローカルな呼称というものはやはりあって。そういう単語が出てくるとみんなザワザワしていました(笑)。ご当地の方に対してのリスペクトにもつながることなので、気を付けましたね。
――音楽メニューは、監督のプランをもとにされていたのですか。
矢野 曲数もふくめ音楽は監督によるプランで動いています。極力小編成で作りたいとの方針でした。
――そもそもシンセ(サイザー)では作らないイメージだったのでしょうか。
矢野 そうですね。基本的には生でやりたいとの意向でした。
――石川(智久)さんはともかく、ZAQさんのイメージでいえば、珍しい気がします。
矢野 あ、そうですね。そもそも劇伴もはじめてとのことですし。ZAQさんにとっては挑戦だったのかなと。ただ、各話での使用曲数が多くないので、申しわけないなという気持ちはありました……。
――各話数にほんの数曲だけが使われる、贅沢なやりかたでしたね。
矢野 どこでどの音楽を使うかといった選曲も監督がなさっているのですが、第6話だけ僕がやっているんですよ。でも、自分がやると若干雰囲気が変わるなと。
――どのように変わってしまうのでしょうか。
矢野 つい曲を入れてしまうんです。音楽で表現してしまう。ノンモン(無音)って、選択としても勇気がいることですし、音響周りだけではなく、他セクションも巻き込むことになるので。こういうやりかたは、監督だからこそできることなのかもしれません。
――なるほど。では、制作した曲数はやはり少なめだった。
矢野 じつはそうではありませんでした。クラシックを各話ごと、スペシャルに用意していたので。それだけで2曲作った話数もあったかな。
――「クラシックを用意した」とは、つまり既存の楽曲をあらたに収録したということですか。
矢野 というより、『スーパーカブ』用に作り直したということです。演奏もあらたにやってはいますが、テンポ感なり尺感も重要だったので、そこも変えているわけですね。
――劇伴用に合わせているのですね。
矢野 そのまま使うとすごく長い曲になりますしね。でも、クラシックって編集しづらいんですよ。神への冒涜感があるというか(笑)。そこにハサミを入れてはいけない気がして。だから、できるだけ原曲に近いものを、使用する尺で収まるように調整してもらっています。それだけでも10曲以上で、それに加えて通常の劇伴があるから、一般的なテレビシリーズにおける曲数分……1クールで35曲くらいですが、割とそれに近い程度になっています。
そうそう、それとは別にピアノのタッチ音も膨大だったんですよ。
――ああ。ふとした瞬間に、ピアノの鍵盤を叩く音が流れますよね。
矢野 これは聴くだけで大変ですよ。打ち合わせで監督と話していたときに4つほど、ちょっとずつニュアンスが違うのがあればいいとなったはずだったんですけど、何十個も来てしまって(笑)。これは大変だぞと。
でも、このタッチ音はとても重要だったんです。音楽はあくまで空気感を表現するためのものなので、そこに主張を見せないようにしていました。逆にタッチ音は、小熊の感情に付けていたんです。カブを見た瞬間、ポーンとタッチ音が響く。これで小熊の高揚した気持ちを表現する、といったことですね。だからこそ、この表現は外せませんでした。
――なるほど。音楽面での監督のディレクションはいかがでしたか。
矢野 いちばん気にされていたのは間(ま)ですね。本当に微妙なんです。「もう半秒下げたい」みたいな、そういう細かい次元の話で。でも、たしかに音楽が半秒ずれるだけでけっこう違うんですよ。そこはおもしろかったですね。音楽編集は僕がやっているんですけど、そのときの指示も何秒何フレームでと。
――フレーム数まで指定があったのですか。音楽編集で、ポイントにされていたのはどういったところだったのでしょう。
矢野 これもやっぱりナチュラルにしたいと。音楽を付けるカットの頭と終わりが決まっているなら、視聴者にバレないように、いかに自然にそこに到達できるか。そういう意味では無理な編集をしないのが大事ですね。少しこぼしてもいいから、自然に曲を終えていく。そんなイメージでやっていました。
――キャスティングについてはいかがでしたか。
矢野 自分がこの企画に参加した時点で、小熊が夜道(雪)さんなのは決まっていましたので、最初に取り組んだのは礼子と椎のオーディションでした。ひと役に30人前後いらっしゃいましたかね。監督とプロデューサー、それからシリーズ構成の根元(歳三)さんとでオーディションを行ったんです。そのときに多数決をしたんですよね。すると、全員きれいに七瀬(彩夏)さんと日岡(なつみ)さんで。これは他の現場ではあまりないことなんです。そこで演技の方向性について、4人が同じ考えを持っていることもわかって。
――では、演技の方向性もほぼほぼ見えていたと。
矢野 ええ。本番のときに変に気合を入れて、演技を(オーディションと)変えないでほしいと思っていたくらいです。
――七瀬さんと日岡さんに決定されたポイントはどこにあったんでしょう。
矢野 礼子は役者としての姿勢にしても、キャラクター作りにしても、夜道さんをリードするような存在であってほしかったんです。ふたりきりでいる時間が作品上多いですしね。そういう意味で七瀬さんがぴったりだったと思います。
椎は、あざとくならないようにしたいと。キャスト次第では、急に場違いな子が来ちゃった感じがするキャラだと思うんですよね。なので「しっかりできる子」側に振りたかったんです。ぴったりハマったんじゃないかと思います。
――実際にアフレコがはじまって、芝居のディレクションはどう考えましたか。
矢野 とくに夜道さんについてですが……。『スーパーカブ』という作品は、少ないセリフではあるものの、リアクションが多いんですよ。台本には「え」とだけ書いてある。でも監督は「え、じゃない」と言うわけです。
――哲学的ですね……。
矢野 (笑)。このせめぎ合いが、とくに序盤は毎週大変で。字を読むのではなく、あくまで息だと。なんなら絵だけで声が入らなくていい箇所もありましたしね。でも、そのニュアンスはなかなか伝えづらいじゃないですか。「『え』じゃなくて『へ』だよ」と言ったりするんですが、本当は「へ」でもない、みたいな……。
とくに小熊って何もしないと、ぶっきらぼうなキャラに見えるんですよ。嫌な感じの返答になることもある。そこは最初から夜道さんに、「嫌な人にならないで」とお話していました。
――セリフは短いですが、だからこそ大変そうです。
矢野 さらにいうと、夜道さんは新人なので、毎回同じ調子にならないんですよね。だからこうしてくれと指示して近づいても、また離れていくことがあったんです。
――芝居を一定にはできないわけですね。
矢野 そう。行けた瞬間、「それだ!」となるんですけど。で、それを繰り返していると聞いている方も判断が難しくなってきて(笑)。「あれ? 最初のほうがよかったかな」みたいな。でも、そこは妥協せずに監督とトライを重ねていきました。
あとは……やっぱりモノローグですかね。
――本編の最初と最後に毎回入る、小熊のモノローグですか。
矢野 ええ。苦労されていました。絵を見ながらやると、どこか頑張っちゃうんですよね。だから、最終的にはもう絵もなしでやろうと。
――そうだったんですか。アニメは見ずに……。
矢野 一度目は絵を見て演じて、大体の間だけ掴んでもらって、あとはもう絵なしでやってしまおう。好きな間でやってくださいと。
――でも、それだと(口)パクと合わなく……いや、そもそもパクはないわけですね。
矢野 そうです。モノローグですからね。全体の尺だけ合っていればいいので。それを毎回繰り返していました。より自然な間で力を抜いてできるかに、いつも挑戦していました。
ただそれが不思議な話で、後半の話数になると一度目でOKが出ることが増えてきたんです。絵を見ても自然にできるようになってきて、そこは彼女の成長だったのかもしれません。
――ナチュラルな芝居という点で、ほかにご苦労はありましたか。
矢野 モブですかね。役者の皆さんが張り切ってくれるんですよ(笑)。でもこういう作品だとそこが浮いちゃうし、夜道さんが主役という時点で、その素朴さも込みで他キャストの演技バランスを考えないといけなかった。だからどう「(演技を)やらないようにするか」。とにかく頑張らないでくれと随分話しました。
たとえば、ガヤひとつとっても、朝登校したら「おはよう」と一斉に言わない。バラバラに会話をさせる。リアルに考えても、友達全員と校門で会うわけじゃないでしょう。それと、放課後のガヤは「疲れさせない」。
――疲れさせない、というのは。
矢野 放課後、授業が終わったあとの描写で、学生たちが「あー」って伸びをする……みたいなね。(アニメでは)けっこう多いじゃないですか(笑)。それはやらない。自然に、あくまでも風景としてそこに存在してくれればいい。でも、これが意外と難しいんですよ。彼らは役者ですからね。張り切った演技は得意なのですが、逆となると意外にね。
――そういうナチュラルな芝居だと、キャストのみなさんは戸惑われたのではないですか。
矢野 ええ。それがパッと意識的にできるのは、相当なベテランですよ。だからもう、何回かやってもらっちゃうんです。それがいちばんいい。
――ああ。疲れもふくめて、もう物理的に力をなくさせてしまう(笑)。
矢野 はい。ただし「ぶっきらぼうにはならないでほしい」と。
――それは難しそうですね。
矢野 でも、普通に生きるってそういうことじゃないですか。ひとつひとつの会話に、気合い入れて「押忍!」なんて言わないですよね。声優はそれができてしまうし、普段はそういう演技を求められるわけです。
――いまのお話をふくめ、ナチュラルな性質が珍しいタイトルだったと思うのですが、こういった作品のご経験は、ほかにありますか。
矢野 いや、これがじつはほぼないんですよ。相当珍しい作品だと思います。アニメって、どうしても戦いが多いじゃないですか。僕も仕事をはじめてからずっとSFやファンタジー、もしくはそれに類する作品が多かったですから。こういうアニメーションはなかなか経験できる機会が少ないので、本当に勉強になりましたよね。
実際、音圧バリバリの戦闘作品のほうがむしろ印象に残らないってことってあるんですよ。「ずっと戦っていたな。あれ? で、どんなドラマだったっけ」となってしまいがちで。『スーパーカブ』のように静かだと、むしろバイクの音が心地よく印象に残りますよね。動を活かすために静が存在する。その考え方は、今後ほかの作品でも活かしていきたいと思っているんです。
●その他の『スーパーカブ』インタビューはこちら
https://st-kai.jp/works/supercub/
●公式サイト
https://supercub-anime.com/